
2026.1.7
経営者のためのSNS戦略(3) 90日で成果を出す「3つの指標」と最小運用チーム
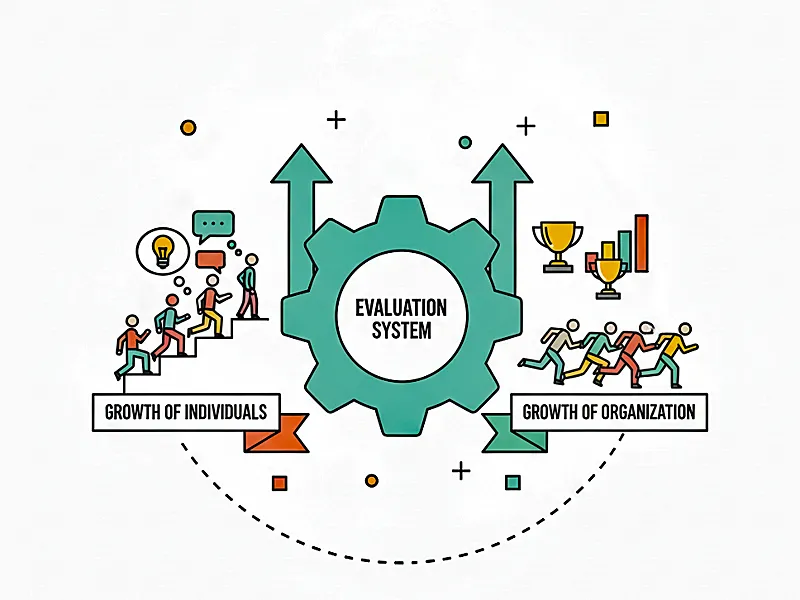
「なぜ、うちの評価制度はうまくいかないのだろうか?」 「結局、上司の好き嫌いで決まっているのではないか?」
多くの企業で、人事評価制度は「人と組織を成長させる仕組み」ではなく、納得感のないまま次期を迎える“年1回の儀式”と化しています。
介護・医療現場から営業、バックオフィス、さらには多拠点やハイブリッド勤務まで、環境や職種が違っても、現場がつまずく理由は驚くほど共通しています。
原因は、複雑な制度そのものではありません。問題は、①曖昧な「評価基準」、②記憶だよりの「運用」、③経営と現場の「戦略のズレ」という、3つのシンプルな失敗に集約されます。
本稿では、多くの企業が陥る典型的な失敗例を交えながら、評価が機能しない「3つの根本原因」を徹底解剖。評価を“儀式”から“成長のエンジン”に変えるため、現場で明日から実践できる具体的な改善ポイントを整理します。
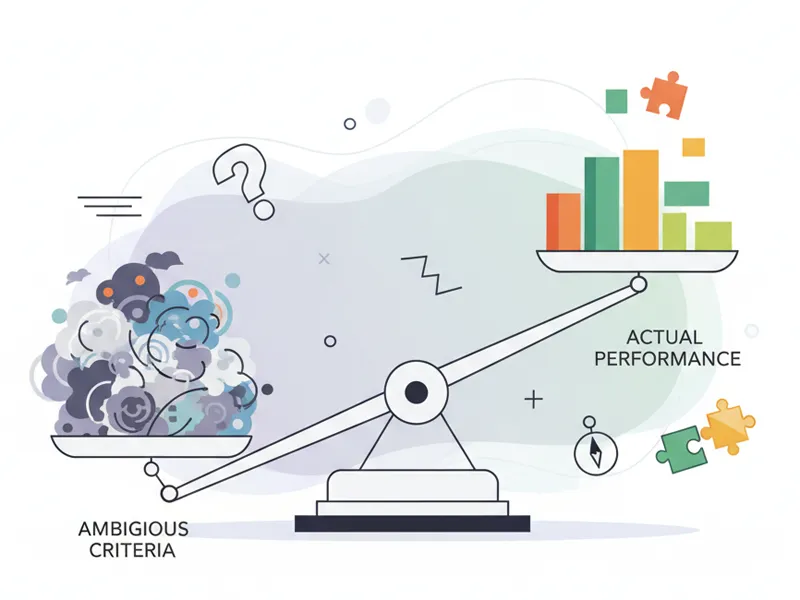
多くの企業で、評価は「S・A・B・C・D」といった記号や、「主体性」「協調性」「責任感」といった“魔法の言葉”で語られます。しかし、これこそが不満の温床です。
ある中堅企業では、全社共通の評価項目として「主体性」を掲げていました。しかし、その定義はどこにもありません。
営業部のA部長は「自ら手を挙げ、新規顧客に果敢にアタックすること」を「主体性=S」と評価しました。
一方、管理部のB部長は「指示された業務の意図を汲み取り、先回りして完璧に仕上げること」を「主体性=S」と評価しました。
期末の評価会議では、A部長とB部長の「S評価」が全く異なる行動レベルを指しているため、議論は紛糾。結果として、声の大きい部門や、数値実績(営業成績)を盾にできる部門の評価が通りやすくなり、部門間の不公平感が拡大しました。
これでは、なぜ自分がその評価(昇給・昇格)になったのか、上司は部下に説明責任を果たすことができません。納得感が得られるはずもありません。
この問題を解決する第一歩が、曖昧な言葉を具体的な「行動」で定義し直すことです。これを「行動アンカー(行動基準)」と呼びます。評価項目ごとに、S・A・B・Cなどの等級別に「どのような行動ができていれば、その評価になるか」を明記するのです。
例えば、「主体性」の行動アンカーは以下のように設計できます。
S: 部署や全社の課題を自ら発見し、周囲を巻き込みながら具体的な解決策を立案し、完遂できる。
A: 指示された業務の範囲を超え、自ら課題を見つけ、具体的な改善策を提案し、実行できる。
B: 指示された業務の背景や意図を理解し、期限内に大きな助言なく自律的に完遂できる。
C: 指示された業務を、上司や先輩の助言を受けながら遂行できる。
このように行動で定義することで、評価者の解釈の余地を減らし、「A部長のS」と「B部長のS」のレベル感を揃えることができます。
次につまずくのが、「全員が同じ基準・同じ配点」で評価されることです。しかし、役割や職種によって、求められる能力の重要度は異なります。
営業職に求められる「協調性」と、介護職に求められる「協調性」、コーポレート部門に求められる「協調性」は、その質も重みも違います。
そこで、評価項目は共通でも、その「配点(ウェイト)」を役割(職群)別に変えることが有効です。
営業職: 業績達成 50%, 新規開拓行動 30%, チーム貢献 20%
介護職: 安全・品質(事故防止) 40%, 利用者・家族満足度 30%, チーム連携(情報共有) 30%
コーポレート職: 業務の正確性・適時性 40%, 業務改善提案 30%, 社内貢献(他部門サポート) 30%
このように、各部門のミッション(期待される役割)に応じて配点を調整することで、評価がより「実態」に即したものになり、現場の納得感が高まります。
評価は、最終的に事業の成果に結びつかなければ意味がありません。しかし、基準が事業目標と連動していないケースも散見されます。
別の失敗例では、経営陣が「新規価値の創出」をスローガンに掲げているにもかかわらず、評価基準の配点は「既存事業の短期的な売上・利益」に極端に偏っていました。
結果、どうなったでしょうか。社員は「新しいことに挑戦して失敗するリスク」よりも、「確実に短期数値を達成すること」を優先します。誰もが保守的になり、イノベーションは停滞しました。
評価基準は、全社の事業KPI(売上目標、利益率、顧客満足度、安全無事故など)と連動させる必要があります。「自分のこの行動が、会社のどの目標に貢献しているのか」が明確になることで、評価は「査定」から「成果への翻訳」に変わります。
評価基準は「行動アンカー × 役割別配点 × 事業KPI連結」で設計する。
曖昧な言葉(主体性、協調性)をやめ、具体的な行動で語る設計に変えることが、納得感への近道です。
代表3項目だけでも行動アンカーを作成する: まずは全社共通のバリュー項目や、特に解釈が割れている項目(例:主体性)だけでも、S/A/B/Cの行動例を作ってみましょう。
期初に「評価項目⇔目標」の対応表を作る: 期初の目標設定(MBO)の際、設定した目標が「どの評価項目(行動アンカー)」の達成に寄与するのか、対応付けを必須にします。
配点表のドラフトを公開し、現場からフィードバックを回収する: 人事部だけで決めず、「なぜこの役割はこの配点なのか」を説明し、現場の意見を吸い上げることで、「押し付けられた制度」感を払拭します。

たとえ素晴らしい評価基準を設計しても、運用がずさんであれば機能しません。最大の敵は「年1回の記憶だより評価」です。
多くの企業では、評価面談は期末に年1回(または半期に1回)行われます。評価者である上司は、部下の1年間の行動をすべて記憶しているでしょうか? 答えは否です。
結果として、「直近効果(Recency Effect)」が多発します。期末に大きな成果を出した部下や、大きな失敗をした部下の印象が強くなり、期初や期中にコツコツと積み上げた貢献は忘れ去られてしまいます。
さらに深刻なのが、ハイブリッド勤務や多拠点運営で広がる「可視性バイアス(Visibility Bias)」です。
こうした「上司から見えやすい」部下が高い評価を受け、リモートワークで黙々と成果を出している部下や、他部門のサポートなど「見えにくい貢献」をしている部下の評価が見落とされがちになります。これでは、不公平感が募るばかりです。
この「記憶だより評価」を防ぐ最も有効な手段は、評価(フィードバック)の「頻度」を上げることです。
年1回の評価をやめ、少なくとも「四半期ごと」に目標の進捗レビューとフィードバックを行います。現代のビジネス環境では、年初の目標が期末には陳腐化していることも珍しくありません。四半期ごとに軌道修正することで、評価が現実の業務と連動し続けます。
さらに重要なのが、日常の「1on1ミーティング」です。これは進捗管理のための「面談」ではなく、部下の成長支援と事実確認のための「対話」です。
この1on1で、上司は「SBIフレームワーク」に基づいた事実(エピソード)を記録・蓄積する習慣をつけるべきです。
S (Situation: 状況): いつ、どこで、どのような状況で
B (Behavior: 行動): 部下が具体的に「何をしたか」(※解釈や評価ではなく、客観的な行動)
I (Impact: 影響): その行動が、周囲や成果に「どのような影響(良い/悪い)」を与えたか
「(S)先週のA社向けコンペ資料の最終チェックで、(B)君が過去の類似案件のデータを自主的に分析し、提案資料のリスクシナリオを補強してくれた。(I)おかげで、質疑応答で懸念点を突かれた際も的確に反論でき、顧客からの信頼が格段に上がったよ。」
これを「月1件」でも良いので記録し続けるだけで、期末の評価面談は「記憶」ではなく「事実(ファクト)」に基づいて行えるようになり、その質は劇的に向上します。
評価の不満で最も多いのが「上司による評価のバラつき(甘辛)」です。A部長は甘く、B部長は辛い。これを放置すれば、部下は「上司ガチャ」に不満を募らせます。
これを防ぐのが「キャリブレーション(目線合わせ)会議」です。これは、評価者(管理職)が集まり、互いの評価基準をすり合わせる場です。
具体的な進め方として、各部門長が「S評価をつけたい候補者」や「D評価をつけたい候補者」について、その根拠となる事実(SBIで記録したエピソード)を持ち寄ります。
「A部長、あなたの部の〇〇さんのS評価の根拠(SBI)を教えてください」
「B部長の部の△△さん(A評価)の行動事例と比べると、〇〇さんの行動は本当にSに値しますか?」
このように、具体的な行動事例を比較検討することで、部門間の甘辛の差が縮まり、全社的な評価の公平性が担保されます。
驚くべきことに、多くの企業で「評価者」になるための必須訓練が行われていません。部下を評価することは、専門的なスキル(観察力、傾聴力、フィードバック力、バイアスへの自覚)を要する高度なマネジメント業務です。
評価者が陥りがちな「評価エラー(バイアス)」について学ぶことは最低限必要です。
ハロー効果: 一つの目立つ長所(例:プレゼンが上手い)に引っ張られ、他も全て良く見えてしまう。
中心化傾向: 揉めるのを恐れ、全員を「B(標準)」につけてしまう。
論理的誤差: 「営業だから積極的なはずだ」と思い込むなど、論理を飛躍させる。
こうしたバイアスを自覚し、SBIを使った客観的なフィードバック演習や1on1のロールプレイングなど、実践的な訓練を必須化すべきです。
結論:年1回評価をやめ、「四半期レビュー+1on1」で事実を蓄積し、評価者訓練を必須化する。 評価運用の品質は「頻度 × 記録 × すり合わせ」で決まります。
月1回の1on1でSBIを最低1件記録する: まずは部下の「良い行動(Good Behavior)」のSBI記録から始め、ポジティブなフィードバックを蓄積しましょう。
四半期に1度、部署横断で評価事例を比較する: まずは「S評価」と「D評価」など、判断が分かれやすい事例を持ち寄り、なぜその評価なのかを議論する場を設けます。
評価者向けの90分ミニ研修を設定する: eラーニングでも構いません。「陥りやすい評価バイアス」と「SBIの基本」について学ぶ機会を全管理職に提供します。

最後の、そして最も根深い原因は、評価制度が「経営」から切り離され、人事部マターの「管理ツール」になっていることです。
ある企業では、中期経営計画で「イノベーションの推進」「挑戦する文化の醸成」を大きく掲げました。しかし、人事評価制度は旧態依然とした「減点主義」のままでした。
新規事業に挑戦し、結果として短期的な赤字を出したチームは、評価が大きく下がりました。一方で、既存事業を守り、ミスなく堅実に運営したチームは高い評価を得ました。
これでは、社員に「経営は挑戦しろと言うが、本音は失敗を許さないのだ」というメッセージを送っているのと同じです。言葉と評価が矛盾すると、社員は賢明にも「挑戦しない」ことを選び、組織の学習と成長は止まります。
別の企業では、「部門横断の連携」「One Team」をバリューに掲げていました。しかし、評価と報酬(インセンティブ)の仕組みは、完全に「個人成果」に紐づいていました。
特に営業部門では、個人別の売上ランキングが日々公開され、インセンティブも個人の達成率のみで決まりました。
結果、何が起きたでしょうか。営業担当者は自分の顧客情報を抱え込み、ノウハウを共有しなくなりました。他部門からの協力依頼は「自分の数字にならない」ため後回しにされ、部門間の連携は著しく低下。内部競争が激化した結果、組織としての総合力(品質や再現性)が低下してしまいました。
評価制度は「経営の翻訳装置」です。経営が目指す「戦略」や「価値観(バリュー)」を、現場の「具体的な行動」に落とし込み、それを実行した人を正しく称賛・処遇する仕組みでなければなりません。
そのために、「戦略マップ」を作成し、経営と評価の連鎖を可視化することが有効です。
経営戦略: 「DX(デジタルトランスフォーメーション)による顧客体験の向上」
全社KGI/KPI: (KGI)顧客満足度 10%向上 / (KPI)新システム導入率 80%
部門の役割行動:
評価項目: 上記の「役割行動」を個人の評価項目(または行動アンカー)に組み込む。
このように、全社戦略から個人の評価項目までが一本の線で繋がっていることを示すことで、社員は「自分のこの仕事が、会社の戦略にどう貢献しているのか」を理解し、日々の行動を変えることができます。
個人の成果だけを追い求めさせると、必ずセクショナリズム(縦割り意識)が蔓延します。医療・介護現場のように、チーム連携がサービスの質や安全に直結する職場では、個人評価偏重は致命的です。
これを防ぐため、評価配分の一部に「チーム評価」を導入します。
配分例:個人評価 70% + チーム評価 30%
チーム評価の対象は、「部門KPIの達成度」「他部門への貢献度(アンケートなどで可視化)」「部門内のナレッジ共有件数」などが考えられます。 チームとしての成果も評価・報酬に反映されることで、「個人の成功」と「チームの成功」の両立を目指すインセンティブが働き、部門を超えた協働が促進されます。
現代の経営環境(VUCA)では、年初の戦略や目標が、期末には陳腐化していることが多々あります。年1回の評価リズムでは、この変化のスピードに追随できません。
理由2で述べた「四半期レビュー」は、運用負荷の軽減だけでなく、戦略への機敏な対応(アジリティ)のためにも不可欠です。市場の変化に応じて、四半期ごとに目標の優先順位や配分を微調整することで、評価制度が「戦略実行ツール」として生き続けます。
結論:評価は経営の翻訳装置。戦略・価値観・報酬と連鎖させ、個人とチームの両方を評価する。 経営戦略と評価のリズムが噛み合ったとき、評価は初めて強力な「行動変容」のドライバーとなります。
チーム配点を暫定20%で試行する: まずは賞与査定の一部だけでも「チーム(部門)評価」の枠を設け、どのような効果(副作用)があるか試してみましょう。
戦略マップのドラフトを作成し、全体共有する: まずは経営企画や人事で、「戦略→KPI→現場の行動」の繋がりを示す1枚のたたき台を作成し、経営陣と共有します。
年次→四半期への移行スケジュールを提示する: いきなり全てを四半期にするのは困難です。まずは「目標レビューだけ四半期」、次に「フィードバックも四半期」など、段階的な移行計画を立てます。
本稿で見てきたように、評価制度が機能しない主因は、制度そのものの複雑さではなく、非常にシンプルな3つのポイントに集約されます。
そして、これらの対策も明確です。
評価制度の改革は、壮大なシステム変更を伴う必要はありません。むしろ、現場が疲弊するだけの複雑な制度は失敗します。
明日から実践すべきは、以下の小さな習慣です。
さらに、これらの運用が定着しているかを測るKPI(例:SMARTな目標設定の適合率、1on1の実施率、SBIの記録事例数、キャリブレーション会議の開催率)を設定し、ダッシュボードなどで可視化することも有効です。
評価は「管理」や「査定」のためにあるのではありません。 「小さく始め、頻度と記録を守る」。 たったこれだけのことを徹底するだけで、評価は“年1回の憂鬱な儀式”から、現場のリアルな「成長習慣」へと変わっていきます。